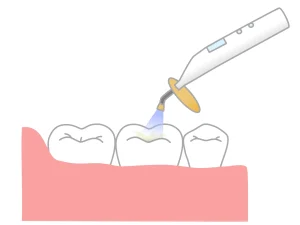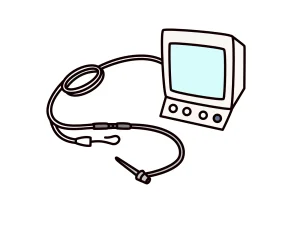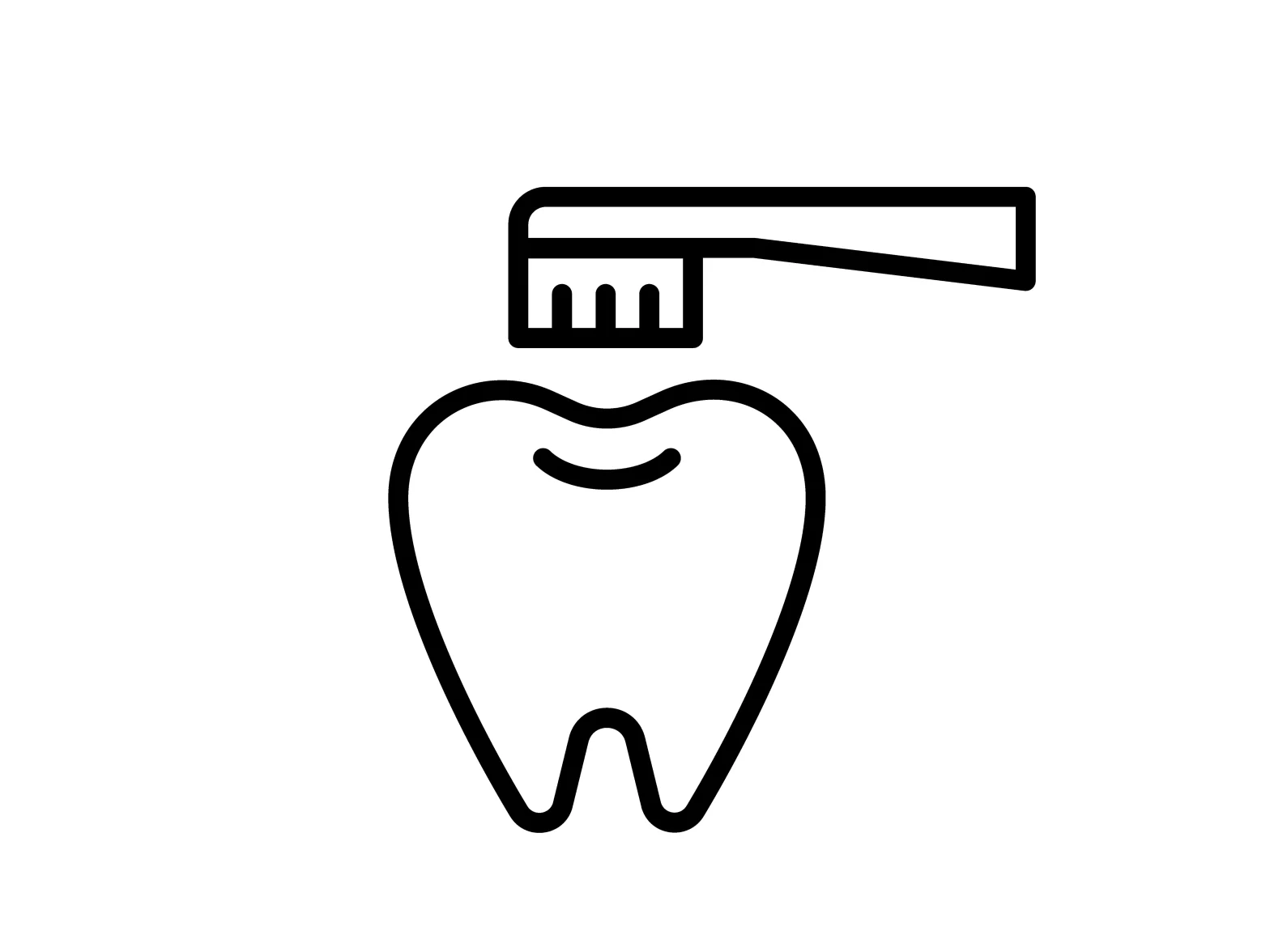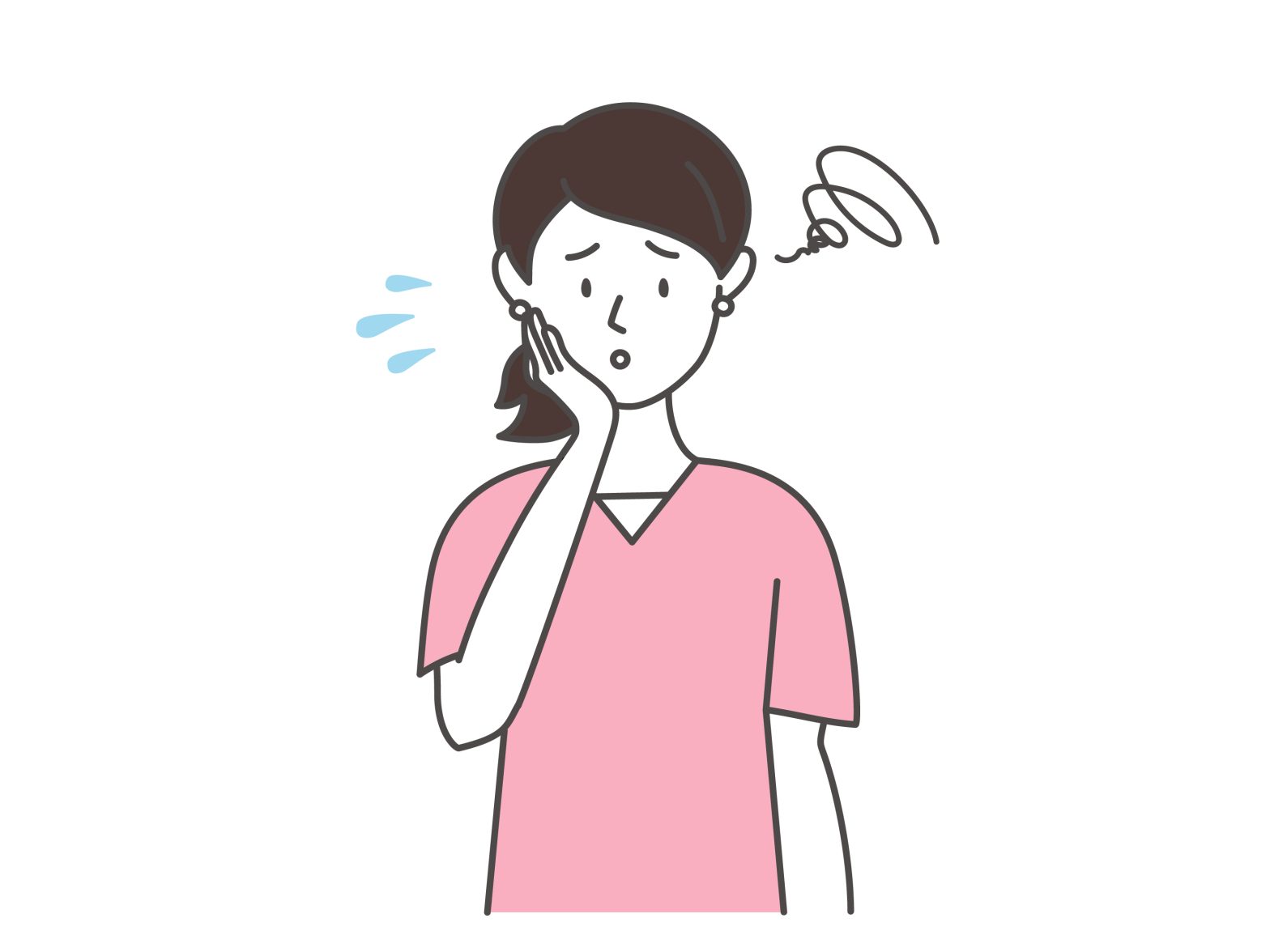虫歯菌は大人同士でもうつる?どの程度でうつるのかも解説

虫歯菌は親子だけでなく大人同士でも唾液を介して移動します。
飲み物の回し飲みやキス、歯ブラシの使い回しなど、日常の何気ない行為にも感染リスクがあります。
それでも普段から口腔ケアや定期検診を徹底すれば、細菌の定着を防ぎやすくなります。
本記事では、虫歯菌が大人間でうつる仕組みや、リスクが高まる行動を解説します。
日常生活で気をつけるポイントや、今日から実践できる予防策も紹介しているのでぜひ参考にしてください。
虫歯菌は大人同士でもうつる
大人の口の中には、虫歯や歯周病の原因となる細菌が数百種以上生息しています。
細菌は唾液に乗って動き回り、グラスの回し飲みやカトラリーの共有、軽いキスでも相手の口腔内へ入り込みます。
細菌は一度に大量にうつるわけではありませんが、繰り返し接触するうちに無視できない数へ増え、定着リスクが高まるのです。
ただし、細菌が移動したからといって即座に虫歯が発症するわけではありません。
口腔環境が整っていれば細菌は排除されやすく、逆にプラークが溜まりやすい状態や唾液量が少ない状態では定着しやすくなります。
大人同士でも「うつる可能性がある」という事実を理解し、日常のケアを徹底することが発症を遠ざける第一歩です。
虫歯菌がうつるメカニズム
虫歯菌は目に見えないほど微小な細菌であり、唾液を介して人から人へと移動します。
一度相手の口に入った細菌は、環境が整えば短時間で仲間を増やしながら定着します。
感染は段階的に進むため、移る段階と定着する段階を分けて理解することが予防の第一歩です。
順番に見ていきましょう。
口腔内の細菌がうつる
虫歯菌はミュータンス菌(Streptococcus mutans)など、虫歯の主因とされる細菌は、主に唾液を通じて人から人へと移動します。
例えば、キスや飲み物の回し飲み、箸やスプーンの共有など、日常的な接触でも簡単に相手の口腔内に入り込む可能性があります。
特に虫歯が進行している人や歯周病がある人は、唾液中に含まれる細菌量が多く、感染リスクが高くなると考えられます。
また、歯に汚れが残っている、口の中が乾燥している場合には、細菌が移動しやすくなります。
見た目が清潔でも、実際には細菌のやり取りが起きていると考えるべきです。
細菌が定着して感染する
移動してきた虫歯菌がすぐに虫歯を引き起こすわけではありません。
相手の口腔内に定着し、活動し始めるには「歯に残った食べかす」や「歯磨き不足」などの条件が揃う必要があります。
さらに、プラークと呼ばれる歯垢が長時間放置されると、細菌がそこに住み着き、酸を生成して歯の表面を溶かしていくのです。
また、唾液の分泌が少ない場合や、口内環境が酸性に傾いていると、細菌の活動はより活発になります。
つまり、細菌の「受け入れ態勢」が整っているときに限って、うつった菌が虫歯として発症しやすくなるのです。
虫歯菌がうつる可能性がある行為
虫歯菌は、キスのような親密な接触だけでなく日常のちょっとした行動でも、人から人へとうつる可能性があります。
特に唾液を介するような場面では、菌が相手の口腔内に入り込みやすくなります。
ここでは、注意すべき代表的な行為を詳しく見ていきましょう。
飲み物の回し飲み
同じコップやペットボトルで飲み物をシェアする行為は、想像以上に唾液のやり取りが行われています。
飲み口に付着した虫歯菌が相手の口に入ることで、菌の移動が起こります。
たとえ一瞬でも、日常的に繰り返されることで菌が定着してしまう可能性が高まります。
特に子どもとの回し飲みは、無意識のうちに虫歯菌をうつしてしまうため注意しましょう。
箸やスプーンなどカトラリーの共有
家族や恋人同士で同じ箸やスプーンを使って食事をすると、口に入れた際に唾液が器具に付着します。
唾液に虫歯菌が含まれていると、次にそれを使った人の口に菌が入り込むおそれがあります。
特に子育て中の親が、自分の箸で子どもに食べ物をあげるような場面は、菌をうつしやすい典型的な行動です。
食器の共用は避け、それぞれ専用のものを使うのが望ましいでしょう。
歯ブラシの共有
「少しだけ使う」という気軽な行動でも、歯ブラシの共有は非常にリスクの高い行為です。
歯ブラシには歯垢や唾液が付着しており、そこには大量の細菌が潜んでいます。
虫歯菌だけでなく、歯周病菌や他の病原菌がうつる可能性もあり、感染症リスクも含めて危険性が高まります。
家族間でも歯ブラシの使い回しは絶対に避けるべきです。
キス
キスは虫歯菌が最も直接的にうつる行為のひとつです。
唇の接触だけでなく、深いキスでは唾液の交換が多くなるため、菌が相手の口腔内に入り込みやすい状態になります。
虫歯のない人同士であれば問題になりにくいものの、どちらかに虫歯がある場合は、相手に感染するリスクが高くなります。
免疫力が下がっている、または口腔環境が悪化しているタイミングでは、虫歯菌が定着しやすいため注意してください。
日常生活で気をつけるポイント
虫歯菌は完全に排除するのが難しい細菌ですが、毎日の生活習慣を少し工夫するだけで定着や増殖を大幅に抑えられます。
ここからは、家庭内や外出先で今日から実践できる対策を紹介します。
ポイント①飲み物や食器の共有前後に口腔ケアをする
外食や家族団らんの席では、同じグラスや皿を使う場面が避けられないこともあります。
共有そのものを完全に禁止するのは難しくても、共有の前にうがいを行い、食後はなるべく早く歯磨きやフロスで汚れを取り除くことで、細菌の定着リスクを抑えられます。
水やお茶で口内をすすぐだけでも唾液に混ざった菌を流せるため、習慣づけると効果的です。
ポイント②歯ブラシを共有しない
歯ブラシには歯垢や唾液が絡みつき、虫歯菌や歯周病菌が繁殖しやすい環境が整っています。
家族や恋人同士でも「ちょっと貸して」は避け、必ず自分専用のブラシを使いましょう。
旅行や外出先で忘れた場合は、使い捨てのブラシを購入するか、指で歯をやさしくこすり水でしっかりすすぐなど代替策で乗り切るのが安全です。
ポイント③免疫ケアをする
睡眠不足やストレスが続くと唾液量が減少し、自浄作用も十分に機能しなくなります。
規則正しい睡眠とバランスの取れた食事で免疫機能を高めることは、虫歯菌の増殖抑制につながります。
ビタミンA・C・Eやポリフェノールなどの抗酸化成分を意識して摂取しましょう。
また、日中はこまめに水分補給することで唾液の分泌も促進できます。
ポイント④歯科検診やクリーニングを定期的に受ける
どれだけ丁寧にセルフケアを続けても、歯と歯の隙間や歯肉の深い部分には磨き残しが生じます。
3〜6ヶ月に一度の歯科検診で虫歯や歯周病の初期サインをチェックし、専門的なクリーニングでプラークや歯石を除去してもらいましょう。
定期受診を習慣化すれば虫歯菌が定着する前にリセットでき、口腔内の長期的な健康につながります。
関連記事:歯周病治療の費用は?進行段階ごとの相場と保険適用について
大人同士でも気をつけたい虫歯菌の感染と予防習慣
虫歯菌は、日常的な行為を通じて大人同士の間でもうつる可能性があります。
キスや食器の共有、飲み物の回し飲みなどで唾液が移ると、細菌も一緒に口腔内へ入り込んでしまいます。
ただし、正しい口腔ケアを続けていれば、菌の定着や虫歯の発症を防ぐのは十分に可能です。
歯ブラシの使い回しを避けること、日々の歯磨きを丁寧に実践することが予防の基本になります。
また、生活習慣を整えて免疫力を維持し、歯科検診を定期的に受けましょう。
日々の小さな意識と行動が、虫歯菌の感染・定着を防ぎ、長期的な口腔の健康を守る基盤となります。

コラム監修者
資格
- 医療法人社団世航会 理事長・歯学博士
- ICOI 国際インプラント学会 指導医
- UCLAインプラントアソシエーション理事
- JAID 常任理事
- 日本顎咬合学会 認定医
- 日本口腔インプラント学会所属
- 日本補綴歯科学会所属
- 日本歯科医師会 会員
- 東京都歯科医師会 会員
- 厚生労働省認定研修医指導医
略歴
- 1997年 明海大学 歯学部入学
- 2003年 同大学 卒業
- 2003年 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 顎口腔機能再構築学系 摂食機能保存学講座 摂食機能保存学分野 博士課程 入学
- 2006年 顎咬合学会 特別新人賞
- 2007年 同大学院 修了 歯学博士所得
- 2007年 東京医科歯科大学 歯学部附属病院 医員
- 2007年 世田谷デンタルオフィス 開院
- 2008年 医療法人社団世航会 設立
- 2013年 明海大学歯学部 保存治療学分野 非常勤助教
- 2014年 明海大学歯学部 保存治療学分野 客員講師
- 2015年 昭和大学歯学部 歯科矯正学分野 兼任講師
- 2016年 明海大学歯学部 補綴学講座 客員講師
- 2020年 日本大学医学部 大学院医学総合研究科生理系 入学
- 2025年 同大学院 修了 医学博士取得
©︎2023 Sekoukai.世航会
都内21院展開!土日診療・当日予約可能!
 医療法人社団世航会
医療法人社団世航会