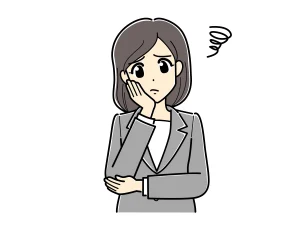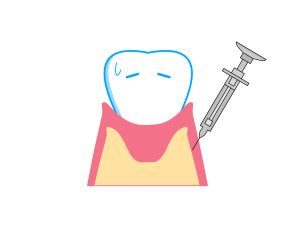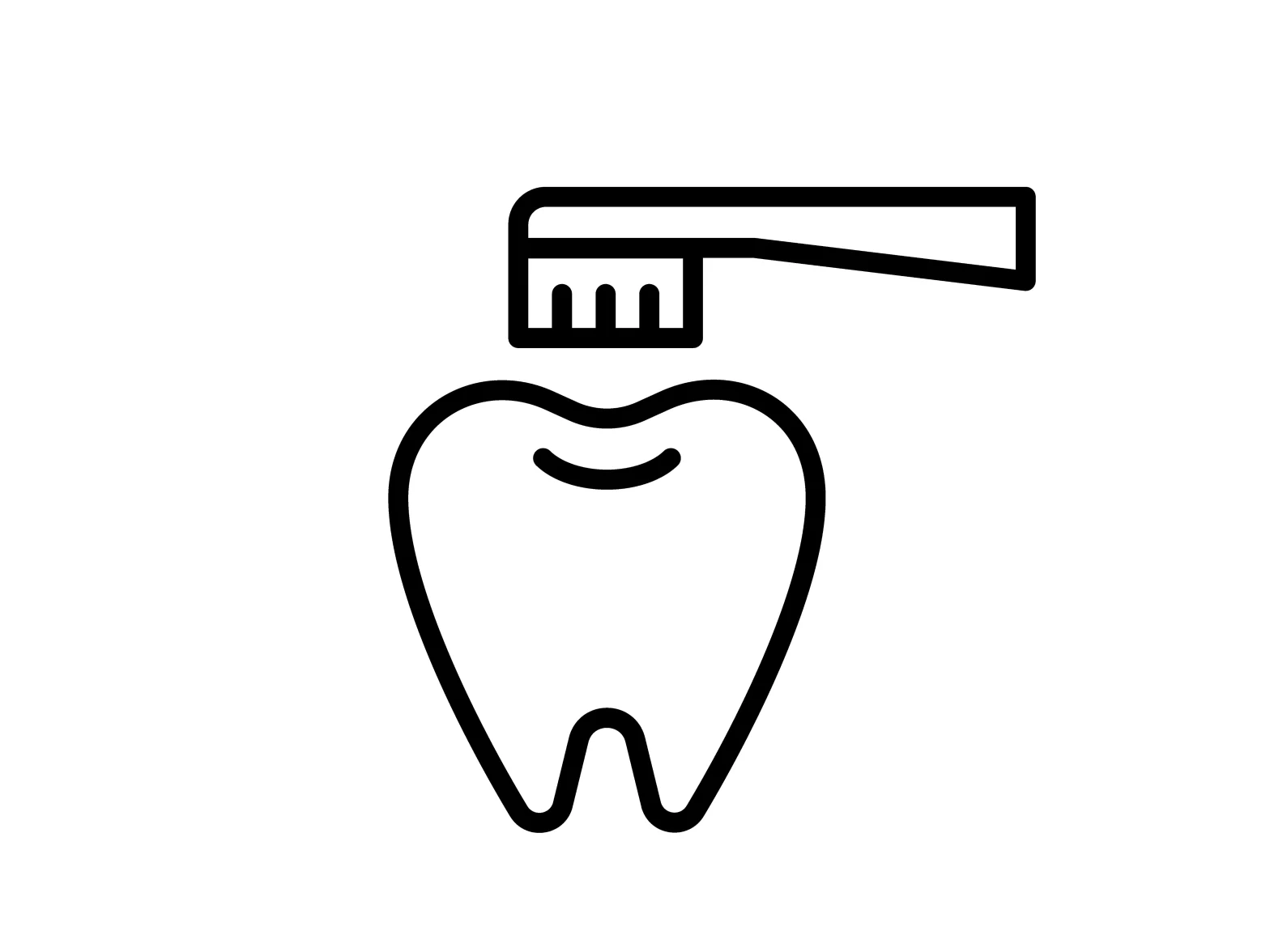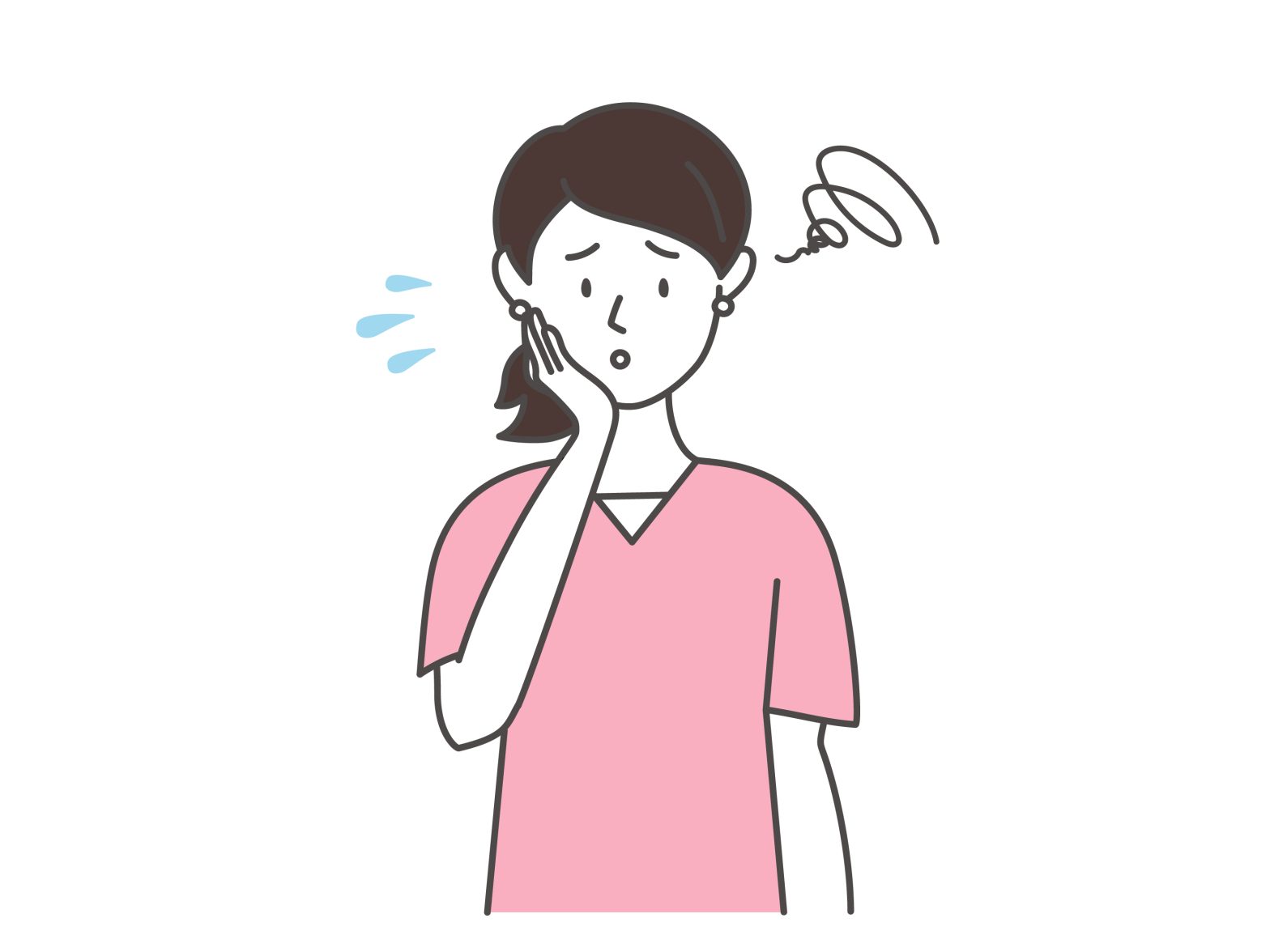虫歯になりやすい食べ物ランキングを解説!虫歯になりにくくするポイントも
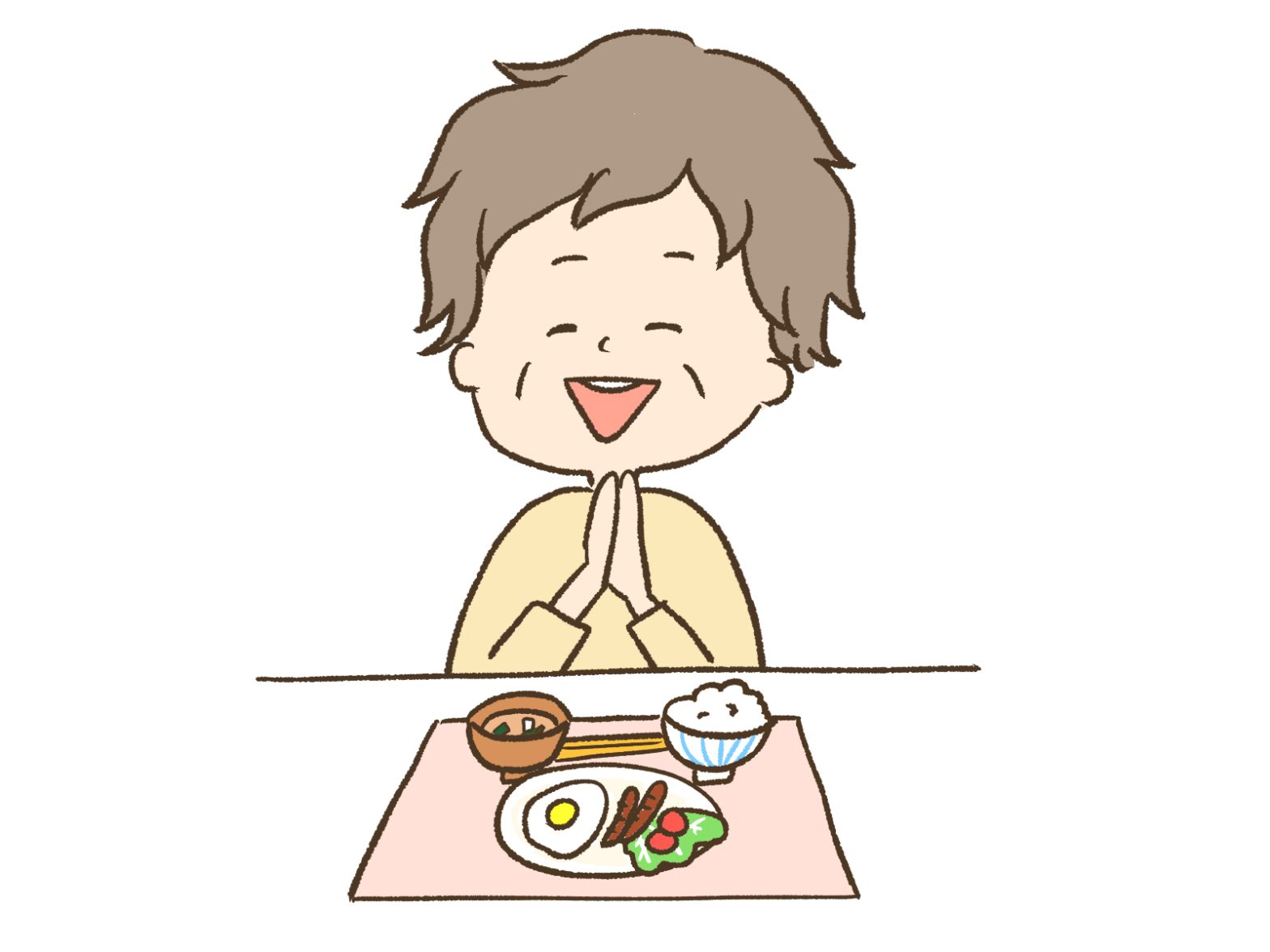
食事を取るとき、虫歯になりやすい食べ物か、虫歯になりにくい食べ物か、と具体的に意識して食事をとる方は少ないでしょう。
本記事では、虫歯になりやすい食べ物や、それを食べた後にどのような方法で予防するのが良いかをご紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。
虫歯はなぜ起こるのか
虫歯は、歯の表面に付着した歯垢の中で、糖分をエサにした虫歯菌が酸をつくり、その酸がエナメル質を溶かしていくことで起こります。
特に砂糖や炭水化物を多く含む食べ物や、だらだらと長時間食べ続ける習慣があると、口の中が酸性の状態になりやすく虫歯リスクが高まります。
まずは、どのような食べ物が虫歯になりやすいのかを知っておきましょう。
虫歯になりやすい食べ物の特徴
虫歯になりやすい食べ物にはいくつかの特徴があります。
ここでは、主な4つの特徴について紹介していきます。
糖分が多い食べ物
虫歯になりやすい食べ物の中でも、もっとも大きな要素となるのが糖分の多さです。
砂糖やブドウ糖、果糖などの糖質は虫歯菌の栄養源となり、歯垢の中で酸をつくり出します。
特にチョコレートやキャラメル、クッキー、アイスクリームのように砂糖を多く含み、頻繁に口にする機会が多い食品は注意が必要です。
また、糖分を含むお菓子や飲み物をダラダラと長時間にわたって摂ると、口の中が酸性の状態になりやすく、虫歯になりやすい環境が続いてしまいます。成分表示を確認しながら、糖分の量や摂取頻度を意識することが大切です。
歯にくっつきやすい食べ物
虫歯になりやすい食べ物の中でも、歯にくっつきやすいものは特に注意が必要です。
チョコレートやキャラメル、クッキーの細かいかけら、ドライフルーツなどは、粘着性が高く歯の溝や歯と歯の間に残りやすい特徴があります。
こうした食べ物が歯の表面に長くとどまると、その部分で虫歯菌が糖分を栄養源に酸をつくり続けるため、エナメル質が溶けやすい環境が続いてしまいます。
おやつに歯にくっつきやすいものを選ぶことが多い方は、量や頻度に気を付けるとともに、食後の歯みがきやうがいを意識して虫歯リスクを抑えることが大切です。
酸性の強い食べ物
虫歯になりやすい食べ物というと甘いものばかりに目が向きがちですが、酸性の強い食べ物にも注意が必要です。
レモンやグレープフルーツなどの柑橘類、酢を使ったドレッシングやマリネ、炭酸飲料などは、お口の中を急激に酸性に傾けてしまいます。
酸性の状態が続くと歯の表面のエナメル質が溶けやすくなり、その後に糖分を摂ったときに虫歯が進行しやすい環境が整ってしまいます。
酸味の強い食べ物や飲み物を摂ったあとは、すぐにゴシゴシ歯磨きをするのではなく、水で軽く口をゆすいだり、時間をおいてからやさしく歯を磨くことが大切です。
精製された炭水化物
「甘くないから大丈夫」と思われがちなパンや白米、うどん、クラッカーなどの精製された炭水化物も、虫歯になりやすい食べ物に含まれます。
精製された小麦粉や白砂糖を多く含む食品は、口の中で素早く糖に分解され、虫歯菌のエサになりやすいことが特徴です。
さらに、パンくずやスナック菓子の細かなかけらは歯の溝や歯と歯の間に残りやすく、気付かないうちに虫歯リスクを高めてしまいます。
主食やおやつを選ぶときは、白いパンやお菓子ばかりに偏らず、全粒粉や野菜、たんぱく質を取り入れながらバランスよく食べるよう心がけましょう。
虫歯になりやすい食べ物ランキング
虫歯になりやすい食べ物にはどのようなものがあるのでしょうか。
ここでは、特に注意しておきたい食べ物をランキング形式で紹介します。
もちろん、これらを絶対に食べてはいけないわけではありませんが、口にする機会が多い方は虫歯リスクが高くなることを理解しておきましょう。
1位:チョコレート
チョコレートは砂糖を多く含み、歯の表面に残りやすいため虫歯リスクを高めます。
糖分は虫歯菌の栄養源となるため、含有量が多いほど虫歯リスクは高くなります。
歯と歯の間に入り込むと、取り除くのが難しくなります。
砂糖や乳成分が多いホワイトチョコは特に注意しましょう。チョコレートが好物な方は、糖分の配合量が少ないものを選ぶのもおすすめです。
カカオ含有量が多いチョコレートは糖分が少なめで、さらにポリフェノールによる抗菌作用も期待できるため、虫歯リスクは比較的低いといえます。
2位:キャラメル
キャラメルはチョコレートと同様に非常に甘く、粘着性も高いのが特徴です。
糖分によって虫歯リスクが高まるだけではなく、治療途中の歯の詰め物にくっつくと取れてしまう恐れがあります。
チョコレートは口の中で噛んで溶かして食べますが、キャラメルは噛まずに長時間舐める人も多くみられます。
口の中に長く糖分が残ればそれだけ細菌が虫歯の原因となる酸を出しやすい環境を作ることになるため、虫歯リスクの高い食べ物です。
3位:クッキー
クッキーには砂糖が多く含まれていることに加え、細かい粒子が歯と歯の間や虫歯の穴に詰まりやすい特徴があります。小さな食べかすが詰まると取り除くのが難しくなりますが、そのまま放置するのは危険です。
頻繁にクッキーを食べる場合は、砂糖不使用で甘さが抑えられたものを選んでみるのもよいでしょう。
4位:飴
飴は口の中で長時間舐め続けることもあり、糖分が歯に接している時間が長いのが特徴です。
糖分が多く長時間口に含むものは、虫歯リスクが高いと考えられます。
特に、唾液の分泌量が少なく、口の中が乾いた状態になることが多い方は、そのままの状態で飴を舐めるのはおすすめできません。
口腔内の糖度が高い状態になってしまい、虫歯リスクがさらに高まる恐れがあります。
これはのど飴にも当てはまります。
のど飴の中にも糖分が多く含まれているものがあり、そういったものを選ぶと虫歯リスクが高まります。
風邪をひいた際などに頻繁にのど飴を舐めたいと考えているのであれば、砂糖不使用のものまたはキシリトール配合のものを選びましょう。
5位:ガム
ガムといえば虫歯予防になるイメージもありますが、種類によって大きく異なります。
砂糖が配合されているガムは多くの糖分が含まれていることから、虫歯になりやすいと考えておきましょう。
また、ガムは長時間口に入れていることが多く、口腔内に長く糖分が残ります。
一方、キシリトールが配合されているガムには虫歯の予防効果があるので、積極的に取り入れてみるとよいでしょう。
キシリトールとは自然界にも存在する成分であり、甘みがあるため食品の添加物として利用されています。
虫歯の原因となる歯垢や酸を作らない特徴があるほか、唾液の分泌を促して汚れを洗い流すこと、酸によって溶けてしまった歯の再石灰化を促すことなどの働きを持ちます。
自然な甘さがあるので、何か口に入れたいけれど虫歯リスクがあるものは避けたいと考えているのであれば、キシリトール配合のガムを選んでみるのもおすすめです。
それ以外の砂糖が使われたガムには注意しましょう。
6位:ポテトチップス
ポテトチップスといえば気軽に食べられてつい食べ過ぎてしまうことがありますが、油分が多く歯にくっつきやすいのが特徴です。
また、原材料であるじゃがいもには多くの糖質が含まれており、この糖質も虫歯菌の栄養源になることから虫歯リスクを高めるといえるでしょう。
7位:ドライフルーツ
ドライフルーツは健康的なおやつとしての印象がありますが、虫歯になりやすい食品の1つです。
フルーツを乾燥させることによって水分が飛ばされ、糖質が凝縮された状態になっています。
また、粘着性が高いことから歯にくっつきやすいのも特徴です。
砂糖を加えていないものだと自然な甘さを楽しめますが、油断しないように注意しましょう。
ドライフルーツをトッピングに使ったお菓子やパンなども同様のことがいえます。
8位:アイスクリーム
アイスクリームには多くの砂糖や乳糖が含まれており、虫歯リスクの高い食べ物です。
さらに口の中に入れると溶けて口腔内全体に広がり、歯の隙間に残りやすくなってしまいます。
特に夜間は唾液の分泌量が減少することもあり、寝る前にアイスを食べる癖がある方は注意したいところです。
虫歯リスクを減らすためには、シュガーレスのアイスクリームを選ぶ方法もあります。
9位:ナッツ類
ナッツ類は健康によいイメージがありますが、硬いため噛み砕いたかけらが歯に挟まりやすい性質があります。
そのまま放置してしまうと虫歯のリスクがあるので注意が必要です。
基本的にナッツはそれほど虫歯リスクが高くありません。
しかし、硬いナッツ類は歯にひびが入ることがあり、そのひびから虫歯が進行する可能性もあります。
硬すぎないもの、無塩・無糖のものを選ぶなどしてみてはいかがでしょうか。
10位:柑橘系のフルーツ
ビタミンCが豊富に含まれているグレープフルーツやオレンジ、レモンといった柑橘類は健康によいことで知られています。
しかし、酸が強いため、歯の表面が溶けて酸蝕症を起こしやすく、虫歯が進行するリスクが高まることにも注意しましょう。
例えば、毎日オレンジジュースやグレープフルーツジュースを飲むといった習慣があると、日々の習慣が虫歯リスクを高めてしまう恐れがあります。
柑橘類に限らず果物は身体によいイメージがありますが、酸性のものには注意が必要です。
関連記事:女性は虫歯が多い?男性と比べて虫歯になりやすい理由と予防方法
虫歯になりにくい食べ物
ここからは反対に、虫歯になりにくい食べ物の特徴と具体例をご紹介します。
カルシウムを含んでいる食べ物
川魚や牛乳・チーズなどの乳製品、納豆や木綿豆腐です。
カルシウムは、歯を作っている象牙質の主要な成分です。カルシウムを摂取しなければ象牙質はもちろん、骨がもろくなってしまいます。
ビタミンAが多く含まれる食べ物
レモンやオレンジなどの柑橘類です。
ビタミンAは、歯の一番外側の部分である、エナメル質を丈夫にします。
ビタミンCが多く含まれる食べ物
緑黄色野菜に多く含まれています。いちご、キウイ、グレープフルーツのような果物にも豊富です。
ビタミンCは、高い抗酸化作用を持ち、カルシウムと結びついて歯を強くしてくれます。
フッ素が含まれる食べ物
いちご、キウイ、グレープフルーツのような果物です。
フッ素は、治療でよく使われている成分で、最近では、歯みがき粉にフッ素を配合しているものが多くあります。歯のエナメル質の再形成を促す成分です。自然の食べ物にも含まれています。
虫歯になりやすい飲み物
虫歯になりやすい飲み物の特徴と例になります。
糖質を含んでいる飲み物全般
炭酸飲料、乳酸菌飲料、スポーツドリンク、果汁100%ジュースはもちろん、お酒や砂糖を入れた飲み物です。
糖質により虫歯菌が繁殖し酸を作り歯を溶かします。
虫歯になりにくい飲み物
虫歯になりにくい飲み物の特徴と例になります。
糖質が含まれていない飲み物
水、緑茶です。
pHが5.5以上で、糖質を含んでいない飲み物です。
食べ物を原因とする虫歯にならないために
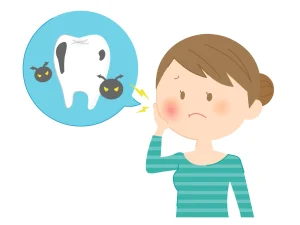
食べ物を原因とする虫歯にならないためには、8つの方法があります。
- 虫歯になりやすい食べ物を避ける
- 寝る前の飲食を避ける
- しっかり噛んで食べる
- ながら食べをやめる
- 甘いものは食後に食べる
- フッ素配合の歯磨き粉を使用する
- 定期的に検診を受ける
- 食べたらすぐに歯磨きする
順番に解説します。
虫歯になりやすい食べ物を避ける
虫歯になりやすい食べ物を避けましょう。
砂糖を多く含んでいる食べ物や飲み物は、虫歯菌の繁殖によって口の中を酸性にします。酸が歯を溶かして虫歯になります。虫歯になりやすい食べ物を食べた後は、歯磨きや口をゆすぐことが大切です。
もし歯磨きや口をゆすぐことができない場合は、虫歯になりやすい食べ物は、避けましょう。
寝る前の飲食を避ける
就寝30分前は飲食を控えましょう。
眠りについたときの口の中は、唾液の分泌が少なく酸性になっています。その状態は、虫歯菌がもっとも繁殖しやすい環境になっています。
就寝の30分前には、歯磨きをして清潔な状態に保ちましょう。
しっかり噛んで食べる
しっかり噛んで食べると、顎や歯が丈夫になるとともに、唾液の分泌がよくなり消化を助けます。唾液には、緩衝作用があり酸性になったお口の中を中性に戻す働きがあります。また、自浄作用があり口の中をキレイにしてくれます。
関連記事:【習慣・食生活別】虫歯の予防方法
ながら食べをやめる
何かをしながら食べる「ながら食べ」はおすすめできません。
スマホを操作しながら、テレビを見ながらといったながら食べは、噛むことに集中できなくなり、唾液の分泌量が少なくなります。
さらに、集中して食事するのと比較して食事時間が長くなることから口腔内が酸性になっている時間も長く、虫歯リスクが高まるのが特徴です。
食事を意識して集中して食べましょう。
甘いものは食後に食べる
虫歯リスクが高い甘いものを食べる場合は、食事の後に食べるのがおすすめです。
おやつとして甘いものを食べた後、歯磨きをしない方も多いかもしれませんが、そのままにしておくと口腔内の虫歯リスクが高い状態が長く続いてしまいます。
食事の一環として甘いものを食べ、その後しっかり歯磨きをすることで、虫歯リスクを抑えることができます。
フッ素配合の歯磨き粉を使用する
フッ素には、歯の表面部分であるエナメル質を強化し、虫歯リスクを抑える働きがあります。
歯磨き粉の中にはフッ素が配合されているものもありますが、どれくらい含まれているかは製品によって異なるので、含有量が多いものを選ぶとよいでしょう。
フッ素が含まれた歯磨き粉を使用する際のポイントは、すすぎすぎに注意するということです。
何度も口をゆすぐと、残しておきたいフッ素まで洗い流してしまいます。
歯磨き後は、小さじ1杯~大さじ1杯程度の少ない水で5秒間、1回程度すすぐようにすることでフッ素を口腔内に長くとどめることが可能です。
また歯医者でもフッ素の塗布が受けられるので、定期的に利用してみましょう。
関連記事:歯磨きしているのに虫歯になるのはなぜ?対策方法も紹介
定期的に検診を受ける
虫歯にいち早く気づき治療につなげるためには、歯医者の定期的な検診が欠かせません。
特に初期段階の虫歯は自分で発見するのが難しいので、定期検診で見つけてもらいましょう。
歯医者で専門的なクリーニングを受ければ、セルフケアでは落とせない汚れを取り除け、虫歯リスクも抑えられます。
食べたらすぐに歯磨きする
甘いものや粘着性の強いものを食べたり飲んだりしたとしても、その後しっかりケアをすれば虫歯リスクは大きく高まりません。
何か食べたあとは口の中が酸性になったり、糖分が残ったりすることで虫歯リスクが高くなるので、食べたらすぐに歯磨きをしましょう。
非常に酸性の強いものを食べたり飲んだりした後は歯のエナメル質がやわらかくなり、そのままの状態で歯磨きをすると歯にダメージを与える可能性があります。
このようなケースでは唾液の働きでエナメル質の硬さが戻るまで30分程度置いてから歯磨きをするとよいでしょう。
食後すぐに歯を磨けないときは、水で口をゆすぐだけでも虫歯予防に効果があります。
虫歯になりやすいポイントを理解して虫歯を予防しよう
虫歯になりやすい食べ物や飲み物を紹介してきました。食べ物が原因で虫歯にならないように、食後のケアによく注意してください。
また、虫歯を予防するためにも、食生活を見直すことから始めてみてはいかがでしょうか。
予防歯科には、定期検診で歯石や歯垢の除去をクリーニングで行い、歯が虫歯にならないように努めることも大切です。
関連記事:医者の定期検診に通う頻度は?メリットと費用を知ろう
世航会デンタルオフィスでは、虫歯治療から予防歯科、歯周病治療まで、幅広い治療をご提供しています。カウンセリングもしっかりと実施しているため、ぜひお気軽にご相談ください。

コラム監修者
資格
- 医療法人社団世航会 理事長・歯学博士
- ICOI 国際インプラント学会 指導医
- UCLAインプラントアソシエーション理事
- JAID 常任理事
- 日本顎咬合学会 認定医
- 日本口腔インプラント学会所属
- 日本補綴歯科学会所属
- 日本歯科医師会 会員
- 東京都歯科医師会 会員
- 厚生労働省認定研修医指導医
略歴
- 1997年 明海大学 歯学部入学
- 2003年 同大学 卒業
- 2003年 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 顎口腔機能再構築学系 摂食機能保存学講座 摂食機能保存学分野 博士課程 入学
- 2006年 顎咬合学会 特別新人賞
- 2007年 同大学院 修了 歯学博士所得
- 2007年 東京医科歯科大学 歯学部附属病院 医員
- 2007年 世田谷デンタルオフィス 開院
- 2008年 医療法人社団世航会 設立
- 2013年 明海大学歯学部 保存治療学分野 非常勤助教
- 2014年 明海大学歯学部 保存治療学分野 客員講師
- 2015年 昭和大学歯学部 歯科矯正学分野 兼任講師
- 2016年 明海大学歯学部 補綴学講座 客員講師
- 2020年 日本大学医学部 大学院医学総合研究科生理系 入学
- 2025年 同大学院 修了 医学博士取得
©︎2023 Sekoukai.世航会
都内21院展開!土日診療・当日予約可能!
 医療法人社団世航会
医療法人社団世航会