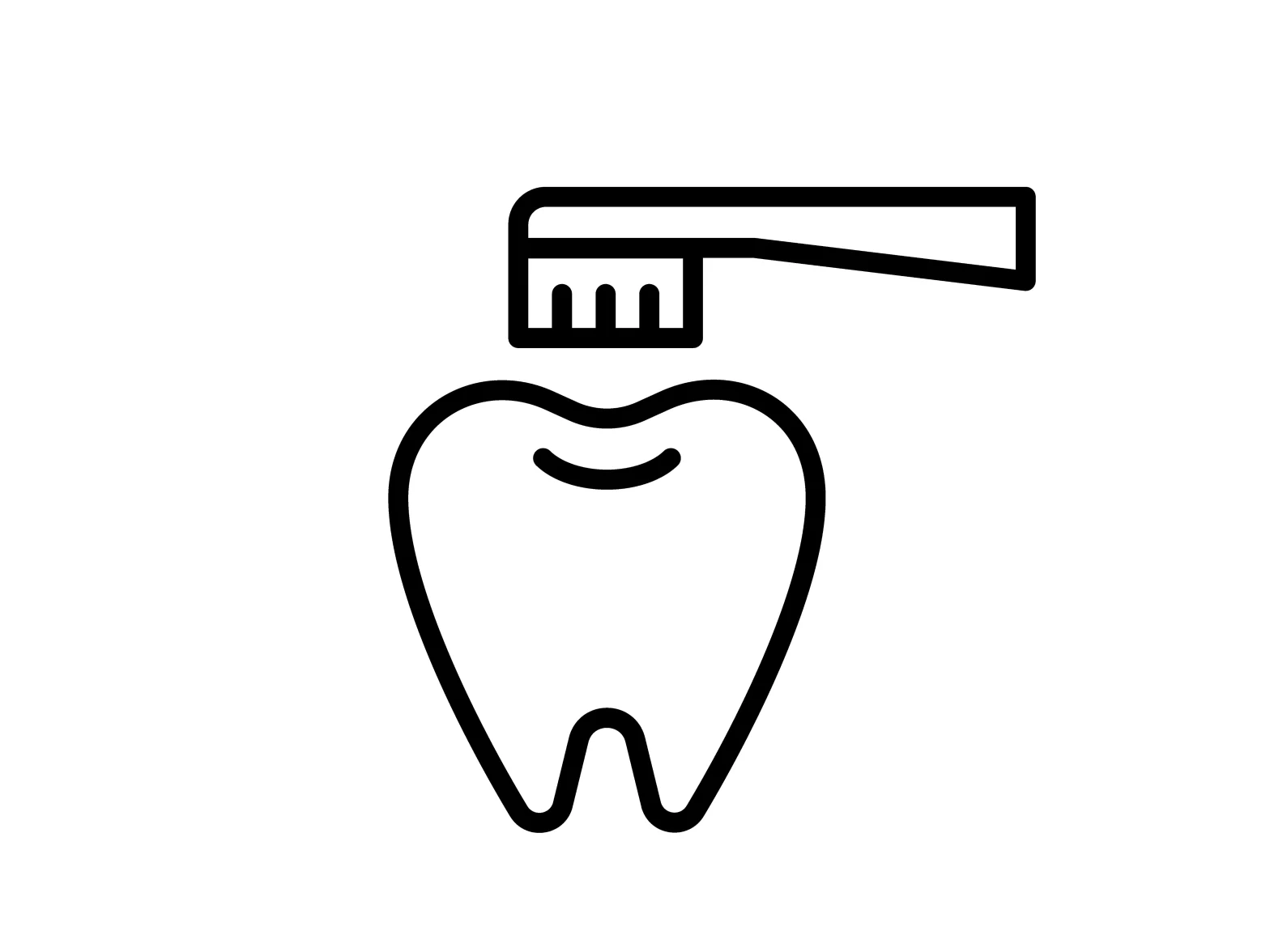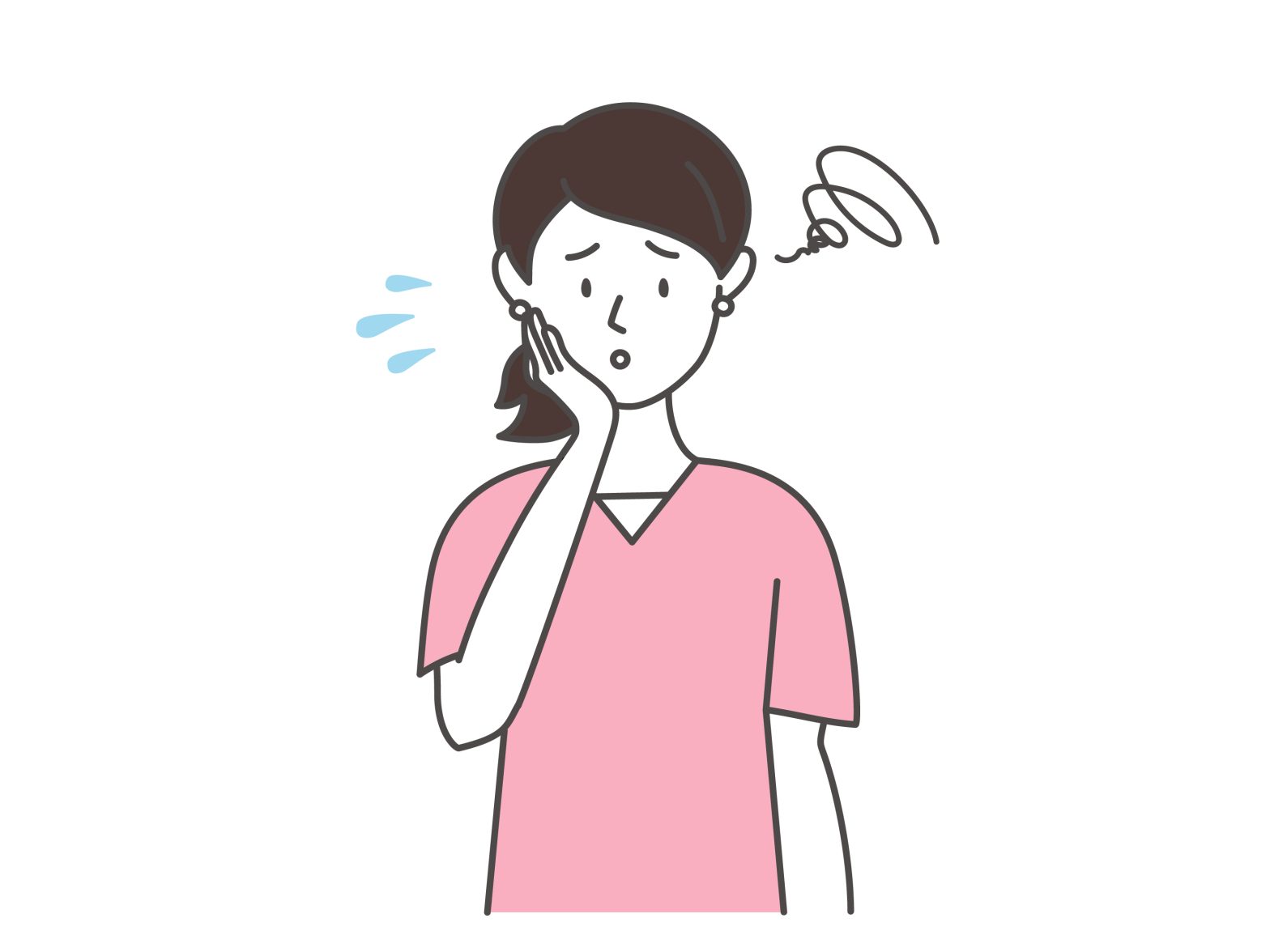歯の詰め物の下も虫歯になる?治療法や予防法について解説

詰め物をした歯でも、その下に虫歯ができてしまうことがあります。
見た目では気づきにくく、痛みも出にくいため、知らないうちに進行しているケースも少なくありません。
本記事では、詰め物の下に虫歯ができる原因や注意すべきサイン、治療方法や予防策まで詳しく解説します。
虫歯の再発を防ぐためにも、ぜひ参考にしてください。
詰め物の下が虫歯になる原因
一度治療を終えた歯でも、詰め物を長期間使用している、またはケアが不十分だと詰め物の下で再び虫歯が進行してしまいます。
これを「二次虫歯」と呼び、気づかないうちに進行するケースが多く注意しなければいけません。
特に銀歯や古い詰め物はリスクが高く、口の中の状態や生活習慣によっても影響を受けやすいと言われています。
ここでは、詰め物の下が虫歯になる主な原因を詳しく解説します。
詰め物の劣化
詰め物は時間の経過とともに少しずつ劣化していきます。
保険適用の銀の詰め物は特に劣化しやすく、熱い飲み物や冷たい食べ物によって日常的に膨張と収縮を繰り返しています。
その結果、歯との適合性が徐々に悪くなり、目に見えないほどのすき間が生じてしまうのです。
そのわずかな隙間から細菌が入り込むと、外見では異常がなくても内側で虫歯が進行してしまいます。
また、詰め物の表面は摩耗しやすく、汚れが付着しやすくなるため衛生的な管理がより難しくなります。
接着剤の劣化
詰め物と歯を密着させるために使われている歯科用セメントも、時間とともに劣化していく素材です。
口の中は常に湿度が高く、食事や飲み物による酸やアルカリの影響も受けるため、セメントは少しずつ溶けてしまいます。
保険診療で使われる接着剤は高性能なものに比べ耐久性が劣るため、接着力が弱まるのが早くなります。
接着剤が劣化すると、詰め物と歯の間に微細なすき間や段差が生まれやすくなり、そこに虫歯菌が侵入して再感染を引き起こす原因に。
自費治療ではより強固な接着力のあるセメントが使えるため、長期的な安定性を求める場合は検討してみましょう。
治療後のメンテナンス不足
詰め物をした後の歯は、もとの天然歯と同じように扱っていては十分なケアが行き届きません。
特に銀の詰め物は表面に細かいキズがつきやすく、そこに汚れやプラークが残りやすいため、丁寧なブラッシングが求められます。
また、フロスや歯間ブラシを怠ると詰め物と歯の境目に汚れが溜まりやすくなり、二次虫歯のリスクが高まります。
さらに、歯ぎしりや食いしばりなどの癖がある人は、詰め物に強い力がかかることで微妙なズレやゆがみが生じ、そこから虫歯が発生するケースもあるでしょう。
こうした問題を防ぐには、定期的に歯科検診を受け、詰め物の状態をチェックして早期に修復や再治療を行うことが理想的です。
詰め物の下に虫歯ができやすいケース
詰め物の下にできる虫歯は目に見えない場所で進行するため、気づいたときにはかなり悪化していることもあります。
痛みやしみる感覚がある場合はもちろん、神経を抜いた歯では自覚症状が出にくいため、知らないうちに虫歯が進行している可能性もあります。
以下のような兆候がある場合は、詰め物の下で虫歯ができている、またはそのリスクが高い状態と考えて良いでしょう。
ケース①治療したときから時間が経っている
詰め物を入れてから何年も経っている場合、経年劣化によるトラブルが起きやすくなります。
特に銀歯や保険適用の素材は耐久年数が限られており、時間の経過とともに詰め物と歯の境目にわずかなすき間ができやすくなります。
すき間から虫歯菌が入り込み、内部で再発する可能性があります。
詰め物を入れてから5年以上経過している場合は、たとえ症状がなくても一度歯科でチェックを受けると安心です。
ケース②食べ物が詰まることが増えた
最近になって、特定の箇所に食べ物が詰まりやすくなったと感じる場合、それは歯と歯の間にすき間が生じているサインかもしれません。
詰め物がわずかにずれていたり変形した場合、隣接する歯との接触が甘くなり、食べ物が詰まりやすくなります。
このような状態が続くとその部分に細菌が繁殖し、詰め物の下や周囲で虫歯が進行しやすくなります。
詰まりを感じたらそのまま放置せず、早めに歯科医院を受診しましょう。
ケース③歯間ブラシやフロスが引っかかる
歯間ブラシやデンタルフロスを使ったときに、以前はスムーズに通っていた部分で引っかかるようになったら要注意です。
それは詰め物がズレている恐れや、詰め物と歯の間に段差やすき間ができている可能性があります。
段差があると、その部分にはプラークや汚れが溜まりやすくなり、虫歯の原因になりかねません。
引っかかりに違和感や痛みを伴う場合は虫歯がすでに進行している可能性もあるため、できるだけ早く診察を受けてください。
詰め物の下の虫歯の見つけ方
詰め物の内部で進行する虫歯は鏡で見ても分からないため、症状が出る頃にはかなり進行しているケースがあります。
早期に発見するには歯科医院での検査が欠かせません。
ここでは、歯科医が実際に行う代表的な診査方法について順番に解説します。
レントゲン撮影する
歯を透過するX線写真は、詰め物の下で黒く透けて見える部分を捉え、虫歯の深さや広がりを把握する手がかりになります。
ただし金属の詰め物はX線を遮断するため、小さな二次虫歯は写りにくいです。
進行した虫歯や金属以外の詰め物であれば比較的確認しやすいので、定期的に撮影し経過を追っていきます。
歯科用マイクロスコープで見る
肉眼では判別しづらいミクロレベルの段差や隙間も、数十倍に拡大できるマイクロスコープを使えば確認しやすくなります。
詰め物の縁にできた微小な隙間や変色、わずかなズレまで観察できるため、虫歯が疑われる箇所をピンポイントで処置できる点がメリット。
レントゲンで映り切らないごく初期の変化を見逃さずに済むのがマイクロスコープの特徴です。
詰め物を外して確認する
痛みや違和感が続いているにもかかわらず、レントゲンやマイクロスコープでも原因が特定できないケースでは、詰め物をいったん外して内部を直接確認する方法が取られます。
詰め物を外すと虫歯が露出するため、その場で削って治療し、新しい詰め物や被せ物に交換するのが一般的です。
時間はかかりますが、原因を確実に取り除けるため再発予防につながります。
詰め物の下の虫歯の治療法
二次虫歯が見つかったときは、進行度に応じて治療の選択肢が変わります。
軽度なら詰め物の取り替えだけで済む場合がありますが、症状が深くなると根管治療や抜歯まで視野に入れなければなりません。
ここでは代表的な3つのアプローチをご紹介します。
詰め物や被せ物を交換する
虫歯が比較的浅く、歯の内部にまで広がっていない場合は、古い詰め物や被せ物を外し、虫歯部分を削ってから新しい補綴物に交換する方法が一般的です。
金属を再利用することもできますが、再発リスクを下げるためにセラミックやジルコニアへ素材を変更する方もいます。
型取りから装着まで1〜3週間程度で完了し、治療後は咬み合わせや審美面のチェックを受ける流れです。
歯の根幹治療を行う
虫歯が神経まで達している、あるいはすでに神経を取った根の内部で再感染が起きている場合は根管治療が必要です。
詰め物を取り外して歯の内部を清掃・消毒し、薬剤で密閉して細菌の再侵入を防ぎます。
治療には複数回の通院が必要ですが、歯根を保存できれば咀嚼機能や骨の健康を守りやすくなります。
治療後は被せ物で強度を補い、再発防止のために定期検診を欠かさないことが大切です。
抜歯する
虫歯が歯根の深部や周囲の骨にまで及び、保存が難しいと判断された場合は抜歯する流れになるでしょう。
歯を失った場合は、噛み合わせを保つためにインプラント・ブリッジ・部分入れ歯などで速やかに補う必要があります。
どの方法にもメリットと注意点があるため、費用・治療期間・メンテナンスのしやすさを歯科医と相談しながら決めましょう。
詰め物の下の虫歯の予防法
二次虫歯を防ぐには、日々のセルフケアと歯科医による定期検診を徹底しなければいけません。
詰め物が入っている歯は天然歯よりも汚れが停滞しやすく、適合性や素材によって再発リスクが変わります。
ここでは、今日から実践できる3つの基本的な対策を解説します。
正しい歯磨きの実施
毎日のブラッシングは二次虫歯予防の要です。
歯ブラシはヘッドが小さく毛先が密なタイプを選び、力を入れすぎずペンを握るように軽く持ちます。
歯と歯茎の境目、詰め物と歯の段差に毛先を当て、小刻みに揺らしながら汚れをかき出すイメージで磨くと効果的です。
さらにフロスや歯間ブラシを併用すれば、歯と歯の間に潜むプラークもしっかり除去できます。
就寝前は虫歯菌が活動しやすいため、歯磨きやフロスによる丁寧なケアを欠かさず行いましょう。
詰め物をセラミック素材に変更
銀歯よりも再発リスクを抑えたい場合は、セラミックなど高精度の補綴物に置き換える方法があります。
セラミックは歯との適合性が高く、温度変化による膨張・収縮も少ないため、すき間が生じにくいのが特徴です。
表面が滑らかで汚れが付着しにくい点や、金属アレルギーの心配がない点もメリット。
審美性が高い一方で保険適用外となり費用負担は増えますが長期的な虫歯予防と快適さを重視する場合には、有力な選択肢の一つとなります。
定期的な歯科検診
セルフケアだけでは落としきれない汚れや、目視できない初期虫歯を早期に発見するには、歯科医院での定期検診が欠かせません。
理想は2〜3ヶ月に一度のペースで受診し、染め出し指導や歯科医によるクリーニングで磨き残しをリセットします。
歯科医がレントゲンやマイクロスコープで詰め物の状態をチェックすることで、二次虫歯の芽を摘み取り、必要に応じて補綴物の微調整や交換を提案してもらえます。
また、検診のたびにブラッシング方法を見直すことで、セルフケアの質も継続的に改善されます。
二次虫歯を防いで歯を守るポイント
詰め物の劣化や接着剤の隙間、ケア不足は二次虫歯を招きます。
小さな違和感でも放置すると痛みなく奥で進行し、根管治療や抜歯に至る可能性も。
歯科医院での定期診断を徹底しつつ、毎日の丁寧なブラッシングとフロスを組み合わせれば再発リスクを大幅に減らせます。
早期発見と予防を軸に大切な歯を守り、口元の健康寿命を延ばしましょう。

コラム監修者
資格
- 医療法人社団世航会 理事長・歯学博士
- ICOI 国際インプラント学会 指導医
- UCLAインプラントアソシエーション理事
- JAID 常任理事
- 日本顎咬合学会 認定医
- 日本口腔インプラント学会所属
- 日本補綴歯科学会所属
- 日本歯科医師会 会員
- 東京都歯科医師会 会員
- 厚生労働省認定研修医指導医
略歴
- 1997年 明海大学 歯学部入学
- 2003年 同大学 卒業
- 2003年 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 顎口腔機能再構築学系 摂食機能保存学講座 摂食機能保存学分野 博士課程 入学
- 2006年 顎咬合学会 特別新人賞
- 2007年 同大学院 修了 歯学博士所得
- 2007年 東京医科歯科大学 歯学部附属病院 医員
- 2007年 世田谷デンタルオフィス 開院
- 2008年 医療法人社団世航会 設立
- 2013年 明海大学歯学部 保存治療学分野 非常勤助教
- 2014年 明海大学歯学部 保存治療学分野 客員講師
- 2015年 昭和大学歯学部 歯科矯正学分野 兼任講師
- 2016年 明海大学歯学部 補綴学講座 客員講師
- 2020年 日本大学医学部 大学院医学総合研究科生理系 入学
- 2025年 同大学院 修了 医学博士取得
©︎2023 Sekoukai.世航会
都内21院展開!土日診療・当日予約可能!
 医療法人社団世航会
医療法人社団世航会