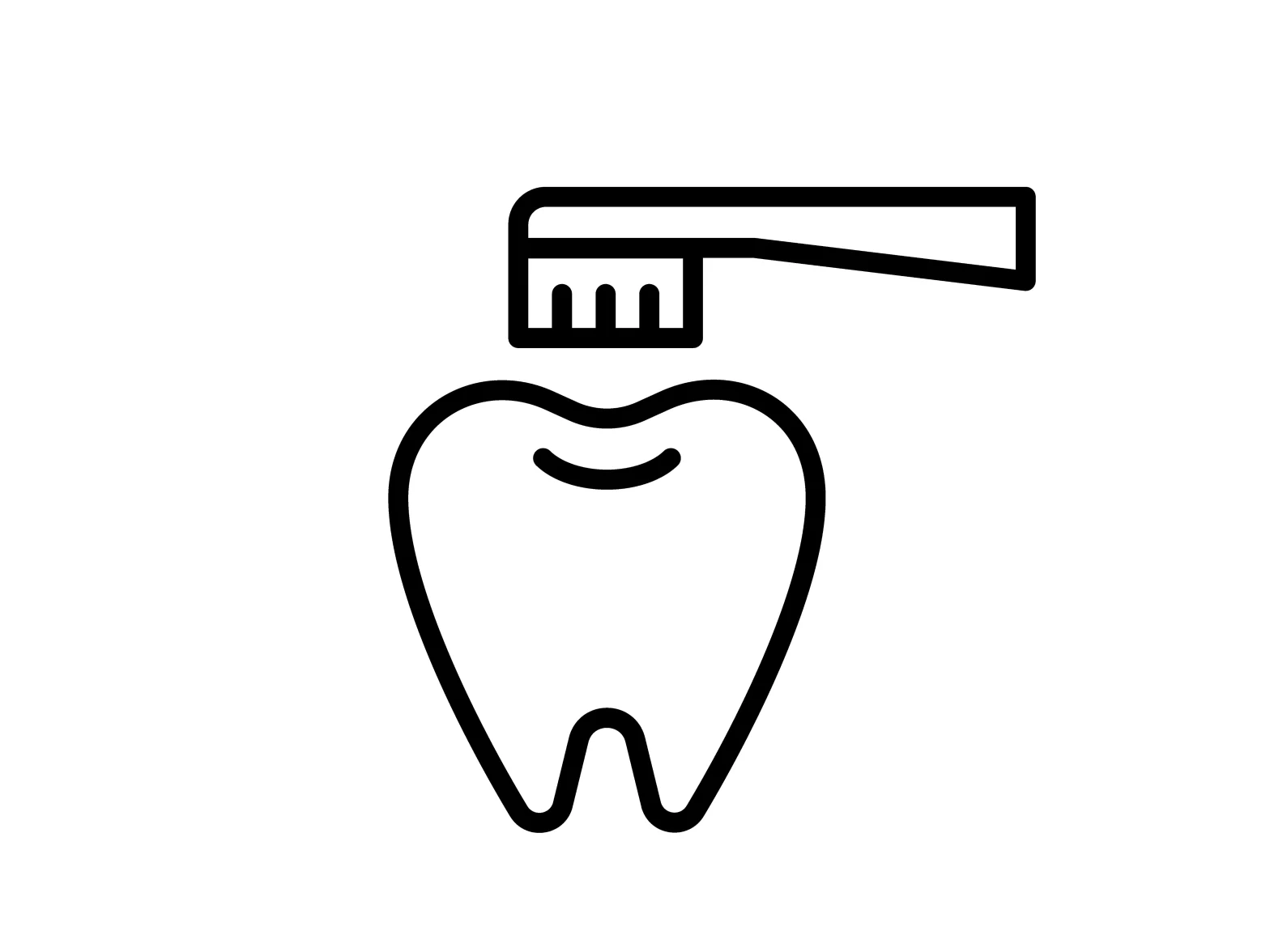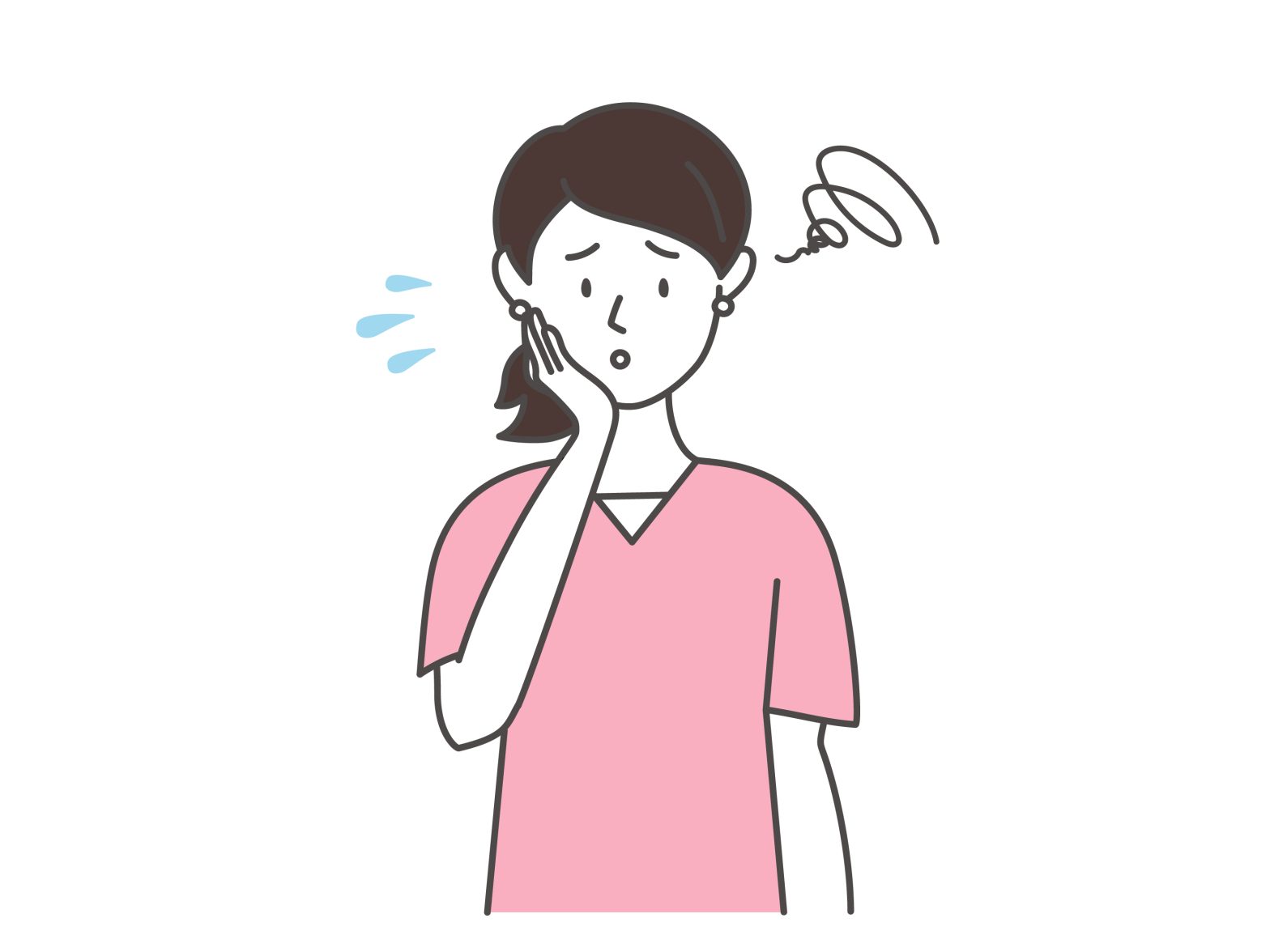子どもはなぜ虫歯になりやすいのか?放置するリスクや進行を抑える方法も解説

子どもの歯は大人よりも虫歯になりやすく、進行も早いため注意が必要です。
自分できちんと歯を磨けなかったり、間食が多かったりすると、虫歯のリスクが高まり、放置によって永久歯や顎の成長にも悪影響を及ぼします。
本記事では、子どもが虫歯になりやすい理由や放置するリスク、進行を防ぐための具体的な対策について詳しく解説します。
日々の習慣を見直し、将来の健康な歯を守るための参考にしてください。
子どもが虫歯になりやすい理由
子どもの歯には大人の歯とは異なる特徴があり、虫歯になりやすい傾向があります。
その背景には、歯の構造的な違いや磨き方の未熟さ、食習慣などが関係しています。
ここでは、子どもが虫歯になりやすい主な理由を3つに分けて詳しく見ていきましょう。
乳歯のエナメル質が永久歯の半分しかない
乳歯の表面を覆うエナメル質は、永久歯に比べて厚みが約半分しかありません。
そのため、虫歯菌が出す酸によって溶けやすく、一度虫歯になると進行がとても早いのが特徴です。
さらに、乳歯は象牙質までの距離も短く、痛みや違和感を抱く頃にはすでに内部で虫歯が大きくなっているケースもあります。
見た目では分かりにくいため、発見が遅れると神経まで達する恐れもあります。
「乳歯はやがて抜けるから大丈夫」という考えは危険で、乳歯の虫歯を放置すると、後から生える永久歯の位置や形に影響することがあるため、早期のケアが重要です。
定期的に歯科検診を受け、必要に応じてフッ素塗布を行うなど虫歯予防を意識的に進めていきましょう。
歯をきちんと磨けていない
子どもが毎日歯を磨いていても、それだけで虫歯を防げるとは限りません。
特に低年齢のうちは手の動きがまだ不器用で、細かい部分まできちんと磨くのは難しいものです。
また、歯と歯の間や奥歯の溝など、汚れが溜まりやすい部分がきちんと磨けていないと、そこから虫歯が進行しやすくなります。
保護者による「仕上げ磨き」は、お子様の年齢に関わらず、少なくとも10歳くらいまでは続けてあげるのが理想です。
さらに、正しい磨き方を知らないまま自己流で磨いていると、どれだけ時間をかけても効果が薄れてしまいます。
歯科医院で定期的にブラッシング指導を受けると、正しい方法を学びやすくなり、家庭でのケアにも自信がつきます。
お子様が自分で磨く練習を続けながら、日々の仕上げ磨きと歯科医のサポートで、虫歯リスクを抑えていきましょう。
間食が多い
子どもは1回の食事で必要な栄養をとるのが難しく、自然と間食が多くなりがちです。しかし、頻繁に何かを口にしていると、虫歯の原因となる「脱灰」の状態が長く続いてしまいます。
脱灰とは、虫歯菌が糖をエサにして酸を出し、歯の表面を溶かす作用のことを指します。
本来、唾液の働きで中和され再石灰化が行われますが、間食が多いと中和の時間が足りず、虫歯の進行が止められません。
特に砂糖を多く含むお菓子やジュースは、虫歯菌の活動を活発にします。
甘いものを長時間かけて食べたり、頻繁に間食を取ったりする習慣は、虫歯リスクを高める典型的な行動です。
間食はなるべく決まった時間に短時間で済ませるようにし、できるだけ歯に優しい食材を選ぶことが大切です。
おやつのあとは口をゆすいだり歯を磨いたりして、虫歯のリスクを減らす習慣をつけましょう。
子どもの虫歯を放置するリスク
乳歯は単に「生え変わる歯」ではなく、永久歯や顎の成長、さらに生活習慣の土台を形づくる重要な役割を担っています。
痛みがあっても受診を先延ばしにすると、口腔内全体の健康が損なわれるだけでなく、将来のセルフケア意識にも悪影響を及ぼします。
ここでは、子どもの虫歯を放置するリスクについて見ていきましょう。
ほかの歯が虫歯になるリスクが高まる
虫歯を抱えた乳歯には大量の虫歯菌が定着し、唾液を介して口腔内に広がります。 いったん菌が増えると、歯垢の中で酸が絶えず産生され、隣の歯冠部や噛み合う歯の溝で急速に脱灰が進みます。
さらに、痛みを避けるために片側だけで噛む癖がつくと、清掃が行き届かない部分が増えプラークコントロールが難しくなるのです。
その結果、1本の乳歯の虫歯が口全体の多発虫歯へと連鎖する可能性が高まります。
永久歯への生え変わりに影響する
一度の虫歯で乳歯の歯根が早期に失われると、後継永久歯が「空きスペースができた」と誤認し、予定より早く萌出することがあります。
自然な生え替わりの順序が乱れると、永久歯が傾いたり捻じれたりして、歯列全体に乱れが生じる恐れがあります。
また、乳歯の根の先に膿が溜まると、すぐ近くで形成されている歯胚が炎症の影響を受け、エナメル質形成不全を引き起こす可能性もあります。
脆弱なエナメル質で生えてきた永久歯は、初期段階から虫歯になりやすく、長期的な治療負担の増加につながります。
顎の発育に悪影響がある
虫歯の痛みを避けるために柔らかい食材ばかりを選び、片側だけで咀嚼する生活が続くと、顎の骨への刺激が不足します。
発育期に左右の筋肉バランスが崩れると、顎の幅や高さが十分に成長せず、その結果、歯列弓が狭くなる可能性があります。
スペース不足は永久歯の叢生や上顎前突など不正咬合を招き、将来的に矯正治療が必要になる可能性が高まります。
噛む力は口腔機能の発達だけでなく、全身の姿勢や呼吸にも関わるため、早期の虫歯治療は顎の健全な成長を守る上でも重要なのです。
将来的な歯医者嫌いにつながる
痛みを抱えたまま受診を先送りにすると、子どもは「歯が痛いのは我慢するもの」と学習し、予防意識が芽生えにくくなります。
さらに、痛みが限界に達したタイミングでの処置は、抜髄や抜歯といった侵襲的な治療につながるため、恐怖心を強める要因になります。
親が早期の治療を決断し、痛みの少ない段階で優しいケアを受けさせることは、「歯医者は痛みを取ってくれる場所」という肯定的な印象を形成します。
こうした経験は将来の定期検診の受診習慣につながり、長期的な口腔健康の維持にも貢献します。
子どもの虫歯の進行を抑えるには
虫歯の進行は早く、放置すると短期間で神経にまで達する恐れがあります。
しかし、生活習慣を見直し、歯科医のサポートを受けることで、進行を防ぎ、再発も抑えられます。
ここでは、毎日の暮らしの中で徹底すべき3つのポイントを見ていきましょう。
間食の時間を決めておく
砂糖を含む食べ物を口にするたび、虫歯菌は酸を作り出し歯の表面を溶かします。
決まった時間に短時間でおやつを済ませることで、唾液の働きによって中和と再石灰化が促進されます。
ジュースやキャンディーをだらだら摂る習慣が続くと、口腔内は長時間酸性のままです。
おやつは30分以内で終わらせ、摂取後に水やお茶で軽くゆすぎ、できればブラッシングを行いましょう。
甘味を完全に禁じる必要はありません。
果物やチーズなど虫歯リスクの低い食品を選び、食べるタイミングを管理することが、無理のない予防策となります。
歯磨き指導を受ける
子どもの手指はまだ発達途上で、歯ブラシを細かく動かすのは難しいものです。
歯科医院のブラッシング指導では、年齢と口腔状態に合わせた磨き方を親子で学べます。
仕上げ磨きは10歳ごろまで続けるのが理想ですが、早い段階で正しいフォームを習得すれば、自立後も効果的な歯磨きが期待できます。
鏡を使い、毛先が歯と歯ぐきの境目に当たっているか確認する練習を重ねましょう。
家庭では、フッ素入り歯磨き剤やデンタルフロスを取り入れ、夜の仕上げ磨きを丁寧に行うことで虫歯の発症率を大幅に下げられます。
定期検診を受ける
乳歯は硬組織が薄く、虫歯の進行が見た目以上に早いため、3〜4か月ごとに検診を受けましょう。
検診では虫歯の早期発見に加え、シーラントやフッ素塗布などの予防処置を受けられます。
クリーニングでプラークと着色を除去した直後にフッ素を塗布すると、歯質強化の効果が高まります。
「歯医者は痛い場所」ではなく、「歯を守ってくれる場所」という肯定的な印象を育むことも、将来的なデンタルIQの向上につながります。
検診日のたびにお口の成長記録を取れば、変化を親子で共有でき、生活習慣の改善にも前向きに取り組めるでしょう。
乳歯のうちからの対策が未来の歯の健康を左右する
子どもの虫歯は進行が早く、放置すると永久歯や顎の発育にまで影響を及ぼす可能性があります。
しかし、仕上げ磨きや定期検診を習慣化し、間食や生活習慣を見直せば虫歯リスクは大きく減らせます。
乳歯の時期から正しいケアを重ね、生涯にわたって健康な歯を守る土台づくりを進めていきましょう。

コラム監修者
資格
- 医療法人社団世航会 理事長・歯学博士
- ICOI 国際インプラント学会 指導医
- UCLAインプラントアソシエーション理事
- JAID 常任理事
- 日本顎咬合学会 認定医
- 日本口腔インプラント学会所属
- 日本補綴歯科学会所属
- 日本歯科医師会 会員
- 東京都歯科医師会 会員
- 厚生労働省認定研修医指導医
略歴
- 1997年 明海大学 歯学部入学
- 2003年 同大学 卒業
- 2003年 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 顎口腔機能再構築学系 摂食機能保存学講座 摂食機能保存学分野 博士課程 入学
- 2006年 顎咬合学会 特別新人賞
- 2007年 同大学院 修了 歯学博士所得
- 2007年 東京医科歯科大学 歯学部附属病院 医員
- 2007年 世田谷デンタルオフィス 開院
- 2008年 医療法人社団世航会 設立
- 2013年 明海大学歯学部 保存治療学分野 非常勤助教
- 2014年 明海大学歯学部 保存治療学分野 客員講師
- 2015年 昭和大学歯学部 歯科矯正学分野 兼任講師
- 2016年 明海大学歯学部 補綴学講座 客員講師
- 2020年 日本大学医学部 大学院医学総合研究科生理系 入学
- 2025年 同大学院 修了 医学博士取得
©︎2023 Sekoukai.世航会
都内21院展開!土日診療・当日予約可能!
 医療法人社団世航会
医療法人社団世航会