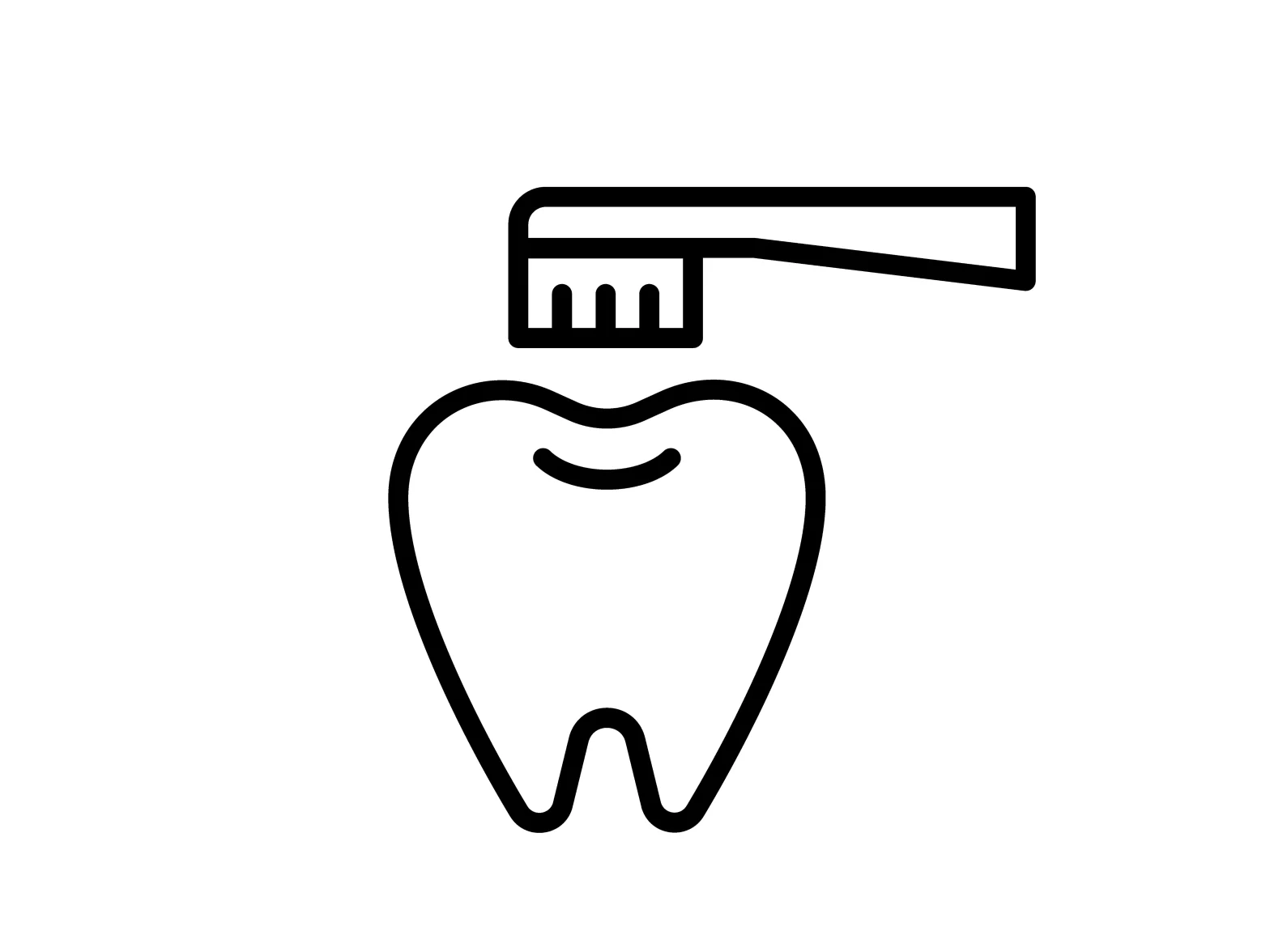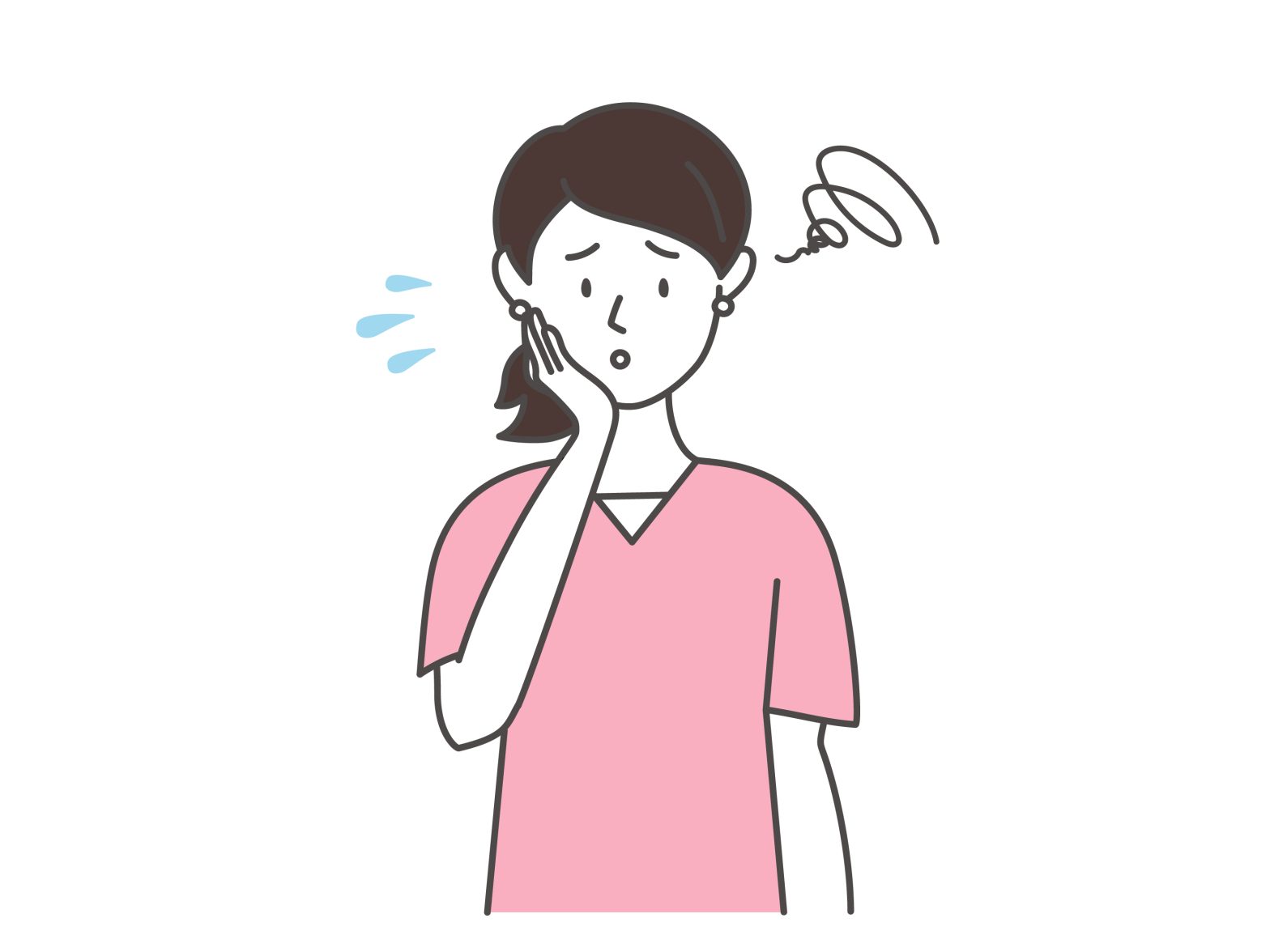親知らずを抜いたあとは歯磨きできる?適切なケア方法を紹介

親知らずの抜歯後は、歯磨きのタイミングや方法を誤ると治癒が遅れてしまうことや、痛みが悪化することがあります。本記事では、安全にケアを進めるための注意点や正しい歯磨き方法を詳しく解説します。
糸や傷口を守る磨き方、強いうがいを避ける理由、食べかすの扱い方といった注意点も併せて紹介します。
適切なケアで治癒を早め、トラブルを防ぎましょう。
親知らずを抜いた当日から歯磨きしてもよい?
抜歯当日でも、基本的には歯磨きをしてかまいません。
ただし、傷口にブラシの毛先が触れると治癒が遅れやすく、痛みが増す可能性があります。
術後の出血は完全に止まるまで半日ほどかかるのが一般的です。
止まりかけた血餅(けっぺい)が歯ブラシや強いうがいで崩れると再出血し、治りが長引く原因となるでしょう。
安全に磨くには抜歯部位を大きく避け、柔らかめのブラシで優しく動かしてください。
歯磨き粉は少量で十分です。泡立ちを抑えればうがいの回数を減らせるため、血餅を守りやすくなります。
親知らずを抜いたあとの歯磨きで注意すべきポイント
抜歯後の口腔内はとても繊細な状態です。
間違った方法で歯磨きやうがいをしてしまうと、傷の回復が遅れることや痛みが悪化してしまいます。
ここでは、抜歯後に注意すべきポイントを解説します。
適切にケアし、トラブルを防ぎながら清潔な状態を保ちましょう。
関連記事:歯の詰め物の下も虫歯になる?治療法や予防法について解説
傷口・傷口の糸に触れない
抜歯した部分は血が固まってかさぶたのような状態になっており、非常にデリケートです。
歯ブラシの毛先がこの部分や縫合糸に触れると、出血や炎症の原因になります。
術後すぐの時期は、縫った糸に毛先が引っかかって痛みを感じ、場合によっては糸が緩んでしまうこともあります。
できるだけ傷口を避けて磨くようにし、無理に近づける必要はありません。
また、柔らかい毛の歯ブラシを使えば刺激をできるだけ抑えられます。
抜糸まではおよそ1〜2週間ほどですので、それまでは特に注意深くケアしましょう。
歯磨き粉を多く使用しない
歯磨き粉をたっぷりつけてしまうと、泡立ちが強くなり何度も口をゆすぐことになります。
しかし、うがいの回数が増えると、せっかく形成された血餅が流れてしまう可能性が高くなります。
血餅は傷口を守る大切な存在です。
これがはがれてしまうと、ドライソケットと呼ばれる強い痛みを伴う状態に進行するリスクがあるのです。
そのため、歯磨き粉はほんの少し、豆粒程度で十分です。
清掃効果に問題なく、むしろうがいの負担を軽減できます。
強くうがいしない
抜歯した部分には自然と血がたまり、血餅というゼリー状のかさぶたができます。
血餅は骨や神経を保護する役割を果たしており、取れてしまうと回復が大きく遅れてしまいます。
強くうがいをすることで、この血餅がはがれてしまう可能性があるのです。
そうなると骨が露出して炎症を起こし、強い痛みに襲われるドライソケットに進展してしまいます。
歯磨き後や食後にうがいしたくなるのは自然なことですが、抜歯後は「とにかくやさしく」を意識してください。
口の中が気になるときは、水を軽く口に含み、刺激を与えないように静かに吐き出す程度にとどめましょう。
食べかすは無理に取らない
傷口に食べかすが入り込んでしまうのは珍しくありません。
しかし、それを無理に取り除こうとするのはかえって逆効果に。
歯ブラシで押し出そうとすることや、爪楊枝でつついてしまうと、粘膜や歯肉を傷つけて感染のリスクが高まります。
抜歯後は炎症が起こりやすいため、慎重に対応しましょう。
もし気になる場合は、殺菌作用のあるマウスウォッシュやウォーターピックを弱めの水圧で使ってみてください。
優しい力ですれば、抜歯後の傷口を守りながら清潔に保てます。
それでも取り除けないときは、無理せず自然に排出されるのを待ちましょう。
過度に心配せず、傷を守ることを優先してください。
親知らずの抜歯後はいつから歯磨きをしてもよい?
麻酔が完全に切れ、お口の感覚が戻ってから実施するのが基本です。
麻酔が効いている間は頬や舌を噛んでも気づきにくく、ブラシによる刺激も感じません。
無理に磨くと傷口を擦ってしまい、出血や痛みが強まるおそれがあります。
抜歯に時間がかかってしまったまたは縫合が施された場合は、患部の治りもゆっくり進みます。当日は出血や痛みが残ることが多いため、抜いた側だけブラシを当てずに済ませても問題ありません。
翌日以降、腫れや痛みが落ち着いてきたら、柔らかめのブラシで周囲をそっとなでるように清掃しましょう。
いずれにしても「感覚が戻ったか」「痛みが落ち着いているか」を確認してから歯磨きを始めてください。
焦らず段階的に再開すれば、傷口を守りながら口腔内の清潔も保てます。
親知らずの抜歯後に歯磨き以外で気をつけるポイント
抜歯後のケアは歯磨きだけではありません。
治癒を妨げる行動や、炎症を招く生活習慣を避けることも大切です。
ここでは、日常生活で注意すべき行動や、症状が出たときの対処法について解説します。
スムーズに回復させるため、以下のポイントをしっかり押さえておきましょう。
喫煙は控える
親知らずを抜いたあとは、タバコは控えるべきです。
喫煙により血管が収縮し、患部への血流が減少します。
血液が十分に届かなくなると傷口の修復が遅れ、治りが悪くなるだけでなく細菌感染のリスクも高まります。
また、タバコに含まれるニコチンや有害物質は免疫力を低下させ、抜歯後の合併症を引き起こすリスクが高まります。
少なくとも傷がふさがるまでは禁煙し、できれば完治するまでタバコを断つよう心がけましょう。
傷口の糸が緩くなったら受診する
抜歯後は歯肉の回復が進むにつれて、縫合した糸が徐々に緩んでくることがあります。
多少の緩みであれば問題ありませんが、大きく動いて歯ブラシに引っかかるような状態になった場合は注意が必要です。
無理に触れてしまうまたは放置すると、出血や感染の原因になります。
緩みが気になるときは、早めに歯科医院で確認してもらいましょう。
痛みや出血を伴う場合は、自己判断せず速やかに受診するべきです。
頬が腫れたら冷やす
抜歯後に頬が腫れるのは自然な反応です。
下の親知らずを抜いた場合は、顔がふくらんだように見えることもあります。
腫れを抑えるには、冷たいタオルや保冷剤を布で包み、軽くあてると効果的です。
冷やしすぎると血行が悪くなり、かえって治癒が遅れるおそれがあるため、長時間冷やし続けないようにしましょう。
腫れが数日続く、痛みが強くなっていくようであれば歯科医院に相談してください。
過度な運動・入浴は避ける
抜歯当日は、血行が良くなる行動を控えてください。
激しい運動や長時間の入浴は体温が上がり、傷口の出血を誘発しやすくなります。
また、アルコールの摂取も同様に血管を拡張させるため、出血や腫れの原因になります。
抜歯当日から翌日にかけては、体に負担をかけないよう安静に過ごすことが大切です。
歯と身体の回復を優先し、十分な休息を取ることが、治癒を円滑に進めるために重要です。
親知らずの抜歯後は正しいケアで回復をサポート
親知らずの抜歯後は、歯磨きのタイミングや方法に気をつけることで傷の治癒をスムーズに進められます。
麻酔が切れた後にやさしくケアを始め、出血や感染を防ぐための注意点を意識し、無理のない生活を心がけましょう。
喫煙や過度なうがい、強い刺激は避け、自然な回復を促すことが大切です。
不安な症状があれば、早めに歯科医院へ相談しましょう。

コラム監修者
資格
- 医療法人社団世航会 理事長・歯学博士
- ICOI 国際インプラント学会 指導医
- UCLAインプラントアソシエーション理事
- JAID 常任理事
- 日本顎咬合学会 認定医
- 日本口腔インプラント学会所属
- 日本補綴歯科学会所属
- 日本歯科医師会 会員
- 東京都歯科医師会 会員
- 厚生労働省認定研修医指導医
略歴
- 1997年 明海大学 歯学部入学
- 2003年 同大学 卒業
- 2003年 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 顎口腔機能再構築学系 摂食機能保存学講座 摂食機能保存学分野 博士課程 入学
- 2006年 顎咬合学会 特別新人賞
- 2007年 同大学院 修了 歯学博士所得
- 2007年 東京医科歯科大学 歯学部附属病院 医員
- 2007年 世田谷デンタルオフィス 開院
- 2008年 医療法人社団世航会 設立
- 2013年 明海大学歯学部 保存治療学分野 非常勤助教
- 2014年 明海大学歯学部 保存治療学分野 客員講師
- 2015年 昭和大学歯学部 歯科矯正学分野 兼任講師
- 2016年 明海大学歯学部 補綴学講座 客員講師
- 2020年 日本大学医学部 大学院医学総合研究科生理系 入学
- 2025年 同大学院 修了 医学博士取得
©︎2023 Sekoukai.世航会
都内21院展開!土日診療・当日予約可能!
 医療法人社団世航会
医療法人社団世航会